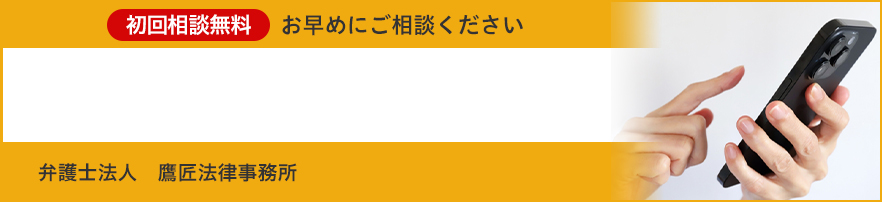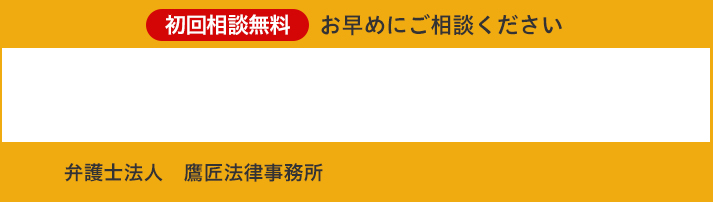はじめに
会社の廃業という言葉がよく用いられますが、これは何のことでしょうか。
平たく言えば「会社をたたむ」ということです。
会社の業績が悪化し、取引先に支払いができなくなった時、従業員に賃金の支払いができなくなった時、取引先の銀行への融資の返済ができなくなった時、中小会社、零細会社の経営者は会社をたたみ、廃業するとの思いが浮かんでくると思います。
会社をたたみ廃業するというと、すぐに倒産という言葉が思い出されますが、廃業イコール倒産ではありません。
事業を縮小し、経営に要する費用を少なくすれば、事業を継続することもできますし、廃業するにしても、会社の負債が会社の資産よりも少なければ、債権者に何らの迷惑はかけませんし、単に事業をやめるだけということになります。
会社の廃業には大きくわけて、解散、破産、民事再生、M&A(事業譲渡)の4つの方法があります。
以下、会社を廃業する際の4つの方法について解説致します。
会社の解散について
裁判所による会社解散決定もありますが、通常の場合、会社が自ら解散を決意することが多いです。
会社が自ら会社の解散を決定する場合には、次の4つの方法があります。
(1) 定款で定めていた会社の存続期間の満了
(2) 定款で定めていた解散事由の発生
(3) 株主総会の決定
(4) 合併による消滅会社
以上は、いずれも会社の意思による解散ですので、何ら問題は発生しないと思います。
これに対して、会社の自らの意思によらない解散事由もあります。
それは次の3つが代表的なものです。
(1) 裁判所による破産手続開始の決定
(2) 裁判所による解散を命じる裁判
(3) みなし解散
(1)の破産手続開始の決定(会社法471条5号)によって、会社を解散するのが破産手続です。
(2)の裁判所による解散を命じる裁判は、解散事由としては最も強制力が強いものです。
公益を確保するために、会社の存続を許すべきでないと認める一定の事由がある場合に、利害関係人の申立てにより、裁判所が解散を命じる解散命令と、会社の総株主の議決権又は発行済株式総数の10分の1以上を有する株主による訴えにもとづいて裁判所が解散判決をする場合があります。
(3)のみなし解散は役員変更などの登記が一定期間行なわれない休眠会社について、法務省の判断で解散の手続きがなされるものです。
この「休眠会社のみなし解散」は会社法472条に定められています。
会社法で義務づけられている登記の変更などを12年間怠っている会社は休眠会社とされ、このような実態のない休眠会社は、社会的にみて存在意義はないものとして強制的に解散させられるものです。
法務省は、この制度を適用して、休眠会社を強制的に解散、整理してしまう休眠会社整理事業を平成26年度以降、毎年10月時点の登記を基準として実施しています。
この事業は、平成25年度までは12年毎に実施されていましたが、平成26年度以降、毎年実施されています。
登記のオンライン化が完成して、毎年実施することが可能になったのです。
法務省は、毎年、3万件前後の会社を強制的にみなし解散させ、会社を消滅させています。
法務省は、このようにして休眠会社が悪用されることを防止しているのです。
このみなし解散は官報による公告がなされ、公告の日から2か月以内に廃業していない旨の届出、又は役員変更等の登記をしないと、強制的に解散したものとみなされるのです。
この対象となる休眠会社には、各地の法務局から個別に通知がなされますが、法務局が宛先にした住所にその会社がないと、この通知が届かないこともあります。
仮に、通知が届かなくても、上記の届出や役員変更等の登記をしないと、みなし解散となってしまいますので注意が必要です。
中小零細会社では、役員の再任の登記がなされずに長期間放置されることもありますので注意する必要があります。
会社を休眠させることは例外的なことですので、会社経営者が休眠を決意するのであれば、思い切って会社の解散をし、清算する方がベターです。
会社の破産について
会社の破産手続は、会社が支払不能、又は債務超過になった場合の会社財産の清算に関する手続であり、この手続により、債権者とその他の利害関係人の利害及び会社と債権者間の権利関係が調整されることになり、これにより会社の財産等の公平な清算がなされ、会社が平穏にたたまれることになります。
そして、破産会社は消滅し、会社の代表者も、以後、安定した社会生活を送ることができるようになります。
この破産手続は、破産法に精通した弁護士がすべて行いますので、会社代表者は弁護士に委任して手続を進めてもらうことがベストです。
地方裁判所に会社の破産申立てがなされると、会社の財産を管理して処分する権限は弁護士の中から選任される破産管財人に移り、会社代表者は、以後、この破産管財人の業務に協力する義務が生じます。
破産というと何となく暗いイメージがつきまといますが、当事務所の経験と実感によりますと、以後の会社代表者の社会生活や経済生活の再スタートになるもので、むしろ、今後に明るい展望をもたらすものとして望ましいものです。
実際、破産手続を利、活用して立ち直った会社経営者を当事務所は何人も見てきています。
会社の破産の申立てには、会社が消滅してしまうというデメリットもありますが、会社が負担していた債務の支払いが全てなくなるということで、会社の代表者は精神的にも楽になり、これらのメリットがデメリットと思われた事柄を大きく上回り、デメリットと思われたことも、デメリットと感じなくなるものです。
会社の負債を会社の代表者個人が連帯保証をしていると、会社の破産と同時に会社代表者自身も自己破産する必要も出てきますが、これも大きなデメリットにはなりません。
会社代表者個人が破産すると、家財道具なども一切失ってしまうと思われがちですが、現実には使い古されている家財道具にはほとんど価値はつかず、そのまま会社代表者のもとに残されることになります。
これ以外にも自由財産といって、99万円までの現金は、破産しても手許に残すことができますし、破産手続が開始された以降に取得した財産(新得財産)は全て自分のものになるのです。又、差押禁止財産や自由財産の拡張が裁判官によって認められた財産、破産管財人が価値がないとして破産財団から放棄した財産も、全て自分のものとなって残ります。
なお、各地の裁判所で異なりますが、東京地方裁判所の例では、一般的には下記の財産は自由財産に含まれるとして扱われ、換価不要とされています。
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
会社の破産申立後の手続の流れは、おおよそ次のとおりとなり、破産が終結するまでには1年を要し、規模の大きい破産の場合には、それ以上の期間を要します。
① 破産申立てと同時に予納金の納付
② 破産管財人の選任
③ 債権者集会
④ 破産手続の終了
こうして会社の破産手続が終結すると、その旨の公告と登記がなされ、それによって会社の法人格が消滅し、会社の登記簿も閉鎖され、名実共に会社はなくなるということになります。
会社の民事再生について
会社の民事再生とは破産の場合と異なり、会社を消滅させず、存続させつつ、会社の債務を減額したりしてもらって、会社の経営体質を強化し、立て直すための民事再生法による整理手続で、勿論、単に事業をやめるということではありませんが、広く言えば廃業と同じような概念にも入りますので、ここで説明したいと思います。
会社の民事再生の手続のおおよその流れは次のとおりです。
会社は民事再生の手続を選択する場合、地方裁判所に対し民事再生の申立てをすることになります。
地方裁判所は、この申立てを受理した後、民事再生の手続開始の要件(支払不能、債務超過のおそれ、予納金納付の有無)があるか否かを判断し、あると判断すれば、民事再生の開始の判断をします。この間に通常、財産の保全の命令が出され、弁護士の中から選任される監督委員によって、会社の監督がなされ、所有する財産の処分、金銭の借入れなどのついては、監督委員の同意が必要になります。
又、民事再生開始の決定がなされる際、併せて会社の債権者による債権届出の期間が定められます。
原則として、この債権届出期間に債権を届出た債権者のみ、手続内で権利を行使することができます。
そして、会社は、手続開始後、遅滞なく会社にある財産の価額を評定しなければならないことになっています。
その後、この手続で一番重要なことですが、会社は、減額を希望する債務の額とその弁済方法を定める再生計画案を地方裁判所に提出しなければなりません。
この再生計画案は、地方裁判所で行われる債権者集会において決議がなされることになっています。
この決議が可決される要件は、民事再生法で次のとおりとなっています。
① 債権者の頭数で過半数の同意(民事再生法172条の3、1項1号)
② 債権者の議決権ベースで2分の1以上の同意(同法同条、2号)
この①、②の要件を満たせば、再生計画案は無事に可決されることになります。
そして、債権者によって可決され、地方裁判所によって認可された再生計画に従がって、以後、債権者に対し弁済することになります。
債権者の可決を得るには、会社は債権者に対し、十分な説明と場合によれば説得をする必要があります。
このことを会社の代表者や担当者が行うことは、なかなか大変で、この仕事は申立代理人である弁護士が主として行うことになります。
弁護士は民事再生法にも精通しており、会社の実状を詳しく説明し、会社の窮状と再生の必要性を述べれば、当事務所の経験でもほとんどの債権者は理解してくれ、再生計画案に賛成してくれます。
会社経営者が、従来、誠実に会社の経営をし、債権者にあまり迷惑をかけていない場合には、再生計画案の可決も容易になります。
認可された再生計画による弁済が無事に履行されれば、めでたく再生手続は終了することになります。
民事再生手続の流れは以上のとおりですが、次に民事再生によるメリットを述べたいと思います。
①経営者が会社経営を継続できる
民事再生手続は、破産手続とは異なり、会社を存続させつつ、債務を整理する手続で、従前の会社経営者がそのまま会社経営にあたることは許されています。
これは会社経営者にとっては大きなメリットだと思います。
②資金繰りが楽になる
民事再生では大幅な債務のカットがなされ、会社の資金繰りは楽になり、仕事さえあれば、会社の再建は円滑に進むことになります。
これも大きなメリットだと思います。
勿論、銀行等の担保権者に対しての民事再生法による規制はありませんので、担保権者とはより一層交流を深め、再生計画に対する理解を得なければなりません。
担保権が実行されれば、会社から重要な資産がなくなり、再生計画による弁済もできなくなってしまうことがありますので、これは大きなデメリットとなり、留意が必要です。
以上のとおり民事再生法による会社の再生には大きな魅力がありますが、会社の仕事がある程度確保でき、債権者に対する弁済も円滑になされることが前提になっていますので、優良な会社でなければ、民事再生法による再生はできないものと考えた方が当事務所の経験でも明白になっています。
M&A(事業譲渡)について
(1) はじめに
M&A(事業譲渡)とは、会社の合併や買収をさすもので、良好な経営をし、価値のある会社を高齢や後継者がいないこと等を理由に、自分の会社を他の会社に吸収合併してもらったり、もしくは、自分の会社を他の会社に買ってもらうことです。
売り手の経営者は、まさしく事実上、会社をたたむことであって、廃業の方法としては対価も入るし、最もハッピーな方法です。
ここでは、最近、多くなっているM&A(事業譲渡)による廃業について説明します。
(2) M&A(事業譲渡)の方法
M&A(事業譲渡)といっても、やり方にはいろいろな方法があります。
大きくわけると、「会社の合併」、「株式譲渡」です。会社のいくつかの事業の内の1つを、他の会社に譲渡する方法もあります。
① 会社の合併
合併とは、2つ以上の会社が1つに統合することをいい、吸収合併と新設合併の方法がありますが、中小・零細会社の場合、吸収合併される方法が一般的です。
吸収合併とは、一方の会社(売り手の会社)が解散し、他方の会社(買い手の会社)が存続する形で行われ、買い手の会社が売り手の会社の債権、債務などの権利義務を包括的に引き継ぐことになります。
中小・零細会社では、会社代表者が会社の株式のほとんどを所有していることが多く、上記が最もポピュラーな方法です。
この方法は、売り手の会社の経営者が買い手の会社に自分の会社の全ての株式を譲渡して、自分の会社は解散し、買い手の会社が存続する形で行われるものです。
新設合併とは、売り手の会社、買い手の会社とも解散し、新たに会社を設立する形で行なわれるものです。
新設された会社が消滅会社の債権、債務などの権利義務を包括的に引き継ぎます。
② 株式譲渡
M&A(事業譲渡)として株式譲渡を行なう場合、売り手の会社の株式所有者である社長等を始めとする経営者は、株式を売却した時点で、売り手の会社の経営から退くことになります。
株式譲渡は株式譲渡契約書を作成して、株式所有者である譲渡人が株式の買い手である譲受人に株式を渡し、株式の対価を得るというもので、何も難しいことはありません。
但し、売り手の会社の株式の対価をどのようにするかは、そんなに簡単ではありません。
ほとんどの中小・零細会社の株式は、証券取引所に上場しておらず、いわゆる未上場株式の価格は直ぐにはわからず、いくつかの算定方法によって評価されなければなりません。
この算定方法には純資産方式、収益方式、比準方式の3つがあります。
ア 純資産方式
売り手の会社の純資産をもとにした算定方法で、これには簿価純資産方式、時価純資産方式の2つがあります。
簿価純資産方式は、帳簿価格による純資産の額を発行済株式総数で割って算出する方式です。
簿価は必ずしも実際の価格を示すものとは限らず、含み益や含み損が多いと、実際の価格と違った価格になってしまいますので注意が必要です。
時価純資産方式は、時価評価した純資産の額を発行済株式総数で割って算出する方式です。
これが実際の価格となるものと思われますが、売り手と買い手は、それぞれが利害関係が違い、評価額で不一致になることも多いです。
イ 収益方式
売り手の会社のキャッシュフローをもとにした算定方法で、売り手の会社の将来的な収益獲得能力等を株価に反映させる点で優れていますが、キャッシュフローの算出等に主観や恣意が入りやすい点に短所があるといわれています。
ウ 比準方式
これは売り手の会社と類似する会社や業種を選択し、この会社と売り手の会社と資産や利益などの要素を比べる方法です。
適切な比較対象の会社を選定できた時には、算定された株価に客観性もありますが、そうでない場合には客観性もなくなり、ひいては、その株価に合理性もなくなることになりますので注意が必要です。
未上場会社の株式の価格算定では1つの算定方式によらず、複数の方式を用い、この平均額を売り手会社の株価とすることも、当事務所は、よく経験しています。
いずれにしても、株価は公認会計士に鑑定してもらうことが多いです。
(3) M&A(事業譲渡)における買い手の会社をさがす方法
自分の会社を他に売りたいと思っても、買主があらわなければ売ることもできませんし、適正な対価を得てハッピーリタイアをし、廃業することもできません。
今ではM&A(事業譲渡)を専門にする会社もありますので、このような売り手と買い手の仲介をする会社に依頼するのも1つの方法ですが、これには勿論費用がかかります。
実際、業績があまり良くない会社は、例え仲介会社に依頼したとしても買い手をさがすことが困難なようです。
(4) 当事務所でも売り手の会社のM&A(事業譲渡)については、過去にも経験し実績もあります。
当事務所はM&A(事業譲渡)業務も取り扱っていますので、お気軽にご連絡いただけたら幸いです。
まとめ
会社の廃業、すなわち、たたみ方には今まで述べましたとおり、いくつかの方法があります。
いずれの方法を選択するにしても、会社の経営者のハッピーリタイアや人生の再出発ができなければ社会的にみても意味がありません。
中小・零細会社と共に歩んだ当事務所は、既に事務所創立50年以上の歴史を有しています。
中小・零細会社を経営する方で、M&A(事業譲渡)を考えている方がいらっしゃれば、当事務所にご相談いただけると幸いです。